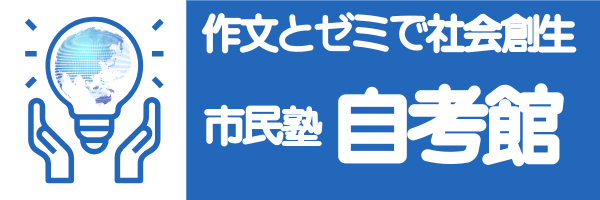ジャーナリスト テレビ朝日元アメリカ総局長 岡田 豊
はじめに
人類は劣化の道をたどっているのであろうか。人間の命をいとも簡単に奪い合う殺戮の日常。欺瞞とフェイクの氾濫。モラルを蹴散らし、事実を軽視し、自己利益を押し通す大国。民主主義の仕組みは揺らぎ、国際秩序は予想以上の速さで変容している。時代は実に大きなパラダイムシフトに入った。
しかし、敗戦以降、「失った80年」を迎えた日本人は思考が止まったままである。このまま、時代の渦に呑み込まれ、途上国化の道をたどるのか。それとも、世界で存在感ある国として立ち上がることができるのか。日本人は、歴史的な岐路に立ち、国家、社会の創り直しを迫られている。日本人の英知が試されている。
1.「フェイクの海」と日本人のリテラシー
筆者は、大学で「情報化社会を生きる 疑う力・創る力」というタイトルで非常勤講師をしている。国内外の課題をテーマに、日本社会が軽視してきたジャーナリズムの存在意義を見いだそうと模索している。講義で学生に次のように訊ねた。「国内外で日々発信されるすべての情報のうち、信用できるのは何割か」。最も多かった回答は「日本は3割」「海外は2割」だった。国内外の7割から8割の情報が信用できず、フェイクあるいはフェイクまがいだという認識である。学生たちの情報に対する不安や危惧が読み取れる。新聞やテレビに対する信頼も低い。身構えてリテラシーを身に付けようとする学生たちに頼もしさを感じる一方、時代の暗澹たる姿が若者たちに映し出されていることを知る。フェイク情報やフェイク映像にまみれた社会で、騙されず、人生の選択や国の進路を誤らずに判断していくことは容易でなくなった。誰が何の目的で、フェイクを放つのか。快感、憎悪、対立、金銭的利益、国家戦略…。動機は様々であろう。我々は、無意識のうちに誘導され、コントロールされるリスクの海に放り出されている。
日本人は、他者の情報を信じ込みやすい性質を持っているという見方がある。「第7回世界価値観調査」[i]によれば、「新聞・テレビから毎日情報を得る」と回答した割合は48カ国中、日本が最も多かった。「新聞・雑誌の組織や信用を信用できる」と答えた日本の割合は70%近くで上位の4位。「テレビの組織や信用を信用できる」は65%近くで8位だった。しかし、これをもって、日本の新聞やテレビが信頼されていると解釈できるわけではない。他の先進国の新聞・雑誌・テレビに対する「信用」は、いずれも40%を下回る。アメリカのテレビに対する「信頼」は22%余に過ぎない。ここから推察できる日本人の性質は「情報を信じ込みやすい」ということである。実状を踏まえて評価すれば、日本人は情報やメディアを見極めるリテラシーのレベルが低い。フェイクの海を無難に泳ぎ切る素養が十分に備わっていないと考えられる。日本人は、自ら考え、自ら判断し、自ら選択する、といった基本的な行動を重視せずにきたのではなかろうか。
メディアとメディアを取り巻く環境も見ておく。言論の自由の擁護などを目的に活動する国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」(本部パリ)は5月、180国・地域を対象にした今年の報道自由度ランキング[ii]を発表した。日本は昨年の70位から66位に順位を上げたが、G7では最下位のままである。日本について「政府や企業が主要メディアの運営に日常的に圧力をかけ、自己検閲も行われている」と批判。メディアと共に、メディアを取り巻く政治や社会などの状況にも厳しい評価を突き付けている。
アメリカは順位を2つ落とし、57位となった。「トランプ大統領が報道の自由の状況を大きく悪化させている」と分析。「メディアに対する政治家の蔑視は一般市民にも及び、ジャーナリストは取材現場で嫌がらせや脅迫、暴行に直面することがある」と指摘した。172位から178位にダウンした中国については「世界最大のジャーナリスト監禁国だ」と批判した。
健全なジャーナリズムは、我々の暮らしや、世界の平和、繁栄にとって極めて重要な機能である。このランキングは相対的なものだが、ジャーナリズムの絶対的なレベルは、世界的に劣化が進んでいる。それゆえ、事実を自ら見極め、解決策を見いだす、市民レベルのリテラシーや思考が一層重要になっている。
2.常識の壁と「自考」
「出る杭は打たれる」。この言葉に象徴されるように、日本は同調圧力が高い同質社会と言っていい。他者にモノを言う、独自の持論を展開する、といった言動は憚られる風潮が残る。そんな日本人は、過去の常識やルール、歴史や権威などに呑み込まれやすく、新しい世界を切り拓きにくいのではないか。フェイクへの耐性の低さに加え、こうした特徴があると考えられる。日本の衰退が加速している理由の一つがここにある。日本社会に必要なのは「出る杭を育てる」文化であろう。
そこで、筆者が提唱するのが、自考(じこう)という思考法である。自考は、多くの日本人が苦手としてきた。自考とは、文字通り、自分の頭で考えるという意味だが、意外にも辞書に載っていない。筆者は自考を次のように定義する。「古びた常識やルールを疑い、自分の心でありのままに感じ取り、自分の頭で自由に考え、オリジナルな自分のやり方を創造的に見いだし、自らと公益のために大胆に実践する」。自考はフェイクに対峙するリテラシーにも直結する。
「自分は自考ができている」。こう思い込んでいる人は多い。しかし、実際、自考を実践できている日本人は少ない。オリジナリティーやイノベーションが広がらず、衰退が進む日本社会の実状がその証左であろう。自考を提唱する拙著[iii]を出した筆者でさえ、常識と脱常識の狭間で日々、葛藤を続けている。
2018年10月。本庶佑・京都大学特別教授は、ノーベル化学賞の受賞発表を受けた記者会見で、科学者を目指す子どもたちに向けて、次のように言った。「研究者になるということにおいて一番重要なのは、何か知りたいと思うこと。不思議だなと思う心を大切にすること。教科書に書いてあることを信じない。常に疑いを持って、本当はどうなってるんだという心を大切にする。つまり、自分の目でものを見る。そして納得する」。「教科書に書いてあることを信じない」。本庶氏のこのメッセージは自考と重なる。常に疑い、自分の目で見て、納得する。これも、フェイクに対峙し、古びた常識が氾濫する社会に立ち向かうために、不可欠なリテラシー[iv]につながる。
例えば、「食べログ」である。「来週の歓送迎会はどの店にしようか」「初デートはどんな店を選ぼうか」。こう迷ったとき、「食べログ」などで、評価が高い店を簡単に選んでしまう。多くの人がこうした評価ツールを利用して日々の選択をしている。便利な存在である。しかし、こうした選択の手法は自考に反する側面がある。自分の目や舌で直接確かめず、現場の店を調べず、自分の頭で考えず、他人の評価を鵜呑みにして、店を選んでいるからである。仮に、その評価に事実に反する加工が施されていたら、我々は的確な選択ができない。仮に、その評価が実態に即し、フェイクでないとしても、思考や選択の幅を自ら狭めていることになる。多忙な日々を過ごす中で、失敗がないように、こうしたツールに依存し、無難な店を選ぶことは無理のない行為であろう。しかし、こうした体質は創造の力を妨げてしまうかもしれない。自らの足で歩き、自らの感覚がピンと来た店に入り、お気に入りの店を探す。評価を他人に依存せず、自らのやり方や価値を自ら見いだす。こうした自考が反映した自立した行動によって、他者がつくった評価を疑い、その評価から自らをいったん切り離し、自分の評価を打ち立てる。こうしたやり方であれば、新しい変化を起こす契機になりうる。
「自考」は、あらゆる学問や実務などの基礎となり、これまで不可能と認識されてきたことを可能にする潜在的な力を秘めている。その持ち場や居場所のことを一番良く知っているのは、その場に日々向き合っている当事者にほかならない。その持ち場や居場所の何をどう変えたら良いかを一番分かっているのも、その場の当事者である。一人ひとりの当事者が、それぞれの持ち場や居場所で、本気で自考を始めるならば、その場に変化が起こり始めるであろう。そうした自考が社会に広がれば、社会を創生するイノベーションが沸き起こり、国を創り直す熱が高まるのではなかろうか。人はオリジナルなアイデアを必ず持っている。変革や創生の主役は、現場を持たない官僚や国会議員ではない。現場を持つ国民や市民である。現場から沸き起こる自考の広がりは、さび付いた常識やルールを淘汰し、未来の芽を育むであろう。
3.アメリカの本気と日本の思考停止
アメリカのトランプ大統領は4月、無謀とも言える高関税政策を世界に振りかざした。世界中から反発が沸き起こり、アメリカに対する信用が損われた。かつて世界を巧みに牽引してきた覇権国の姿は、もうそこにはない。別な角度から俯瞰すると、筆者には、アメリカが悲鳴をあげ、もがいているようにも見える。「アメリカはもう一度偉大な国になりたいのです。でも、限界が近づいているので、みなさん、どうか力を貸してください」。トランプ大統領がこう懇願していると想像してみる。トランプ関税の狙いは、巨額の貿易赤字の削減であり、ひいては巨額の財政赤字の削減である。各国の信頼を損ねてまで突き進むトランプ政権は、プライドをかなぐり捨てている。あえて肯定的に捉えれば、トランプ政権は国家の立て直しに本気になったと解釈できる。
ひるがえって日本はどうか。トランプショックに見舞われた4月、石破茂首相は「国難とも称すべき事態」と言及した。しかし、石破首相、政府の面々、与野党の国会議員からは、未来を切り拓く本格的な政策論が出てこない。まるで思考が止まっているようである。夏の参院選に向け、石破首相は「2040年に名目GDP1000兆円」「国民の平均所得を5割以上上昇」と打ち上げた。だが、根拠となる具体的な成長戦略は示されず、実現に懐疑的な見方も根強い。岸田前政権が掲げた「資産所得倍増計画」を覚えている人も多くない。さらに与党は、給付金という名のバラマキを実施する方針を示した。野党もこぞって減税を主張する。困窮極まった国民には即効性のある支援が必要だが、その場しのぎの単なるバラマキや減税だけでは、財政を悪化させるポピュリズム政治に成り下がる。
言うまでもなく、日本の国家財政状況はアメリカより悪く、破綻状態に向かうリスクが徐々に積みあがる。「自国通貨建てて国債を発行している限り、赤字国債を発行しても、日本は財政破綻しない」などとうそぶく無責任な一部の専門家や国会議員の言葉を鵜呑みにしないことが肝要である。5月、日本国債の30年債と40年債の利回りが過去最高を更新した。一時的とはいえ、不穏なサインである。トランプ関税を背景に米欧の国債利回りも上昇したが、GDPと比較した日本の財政状況は突出して悪い。国家財政は、理屈だけで説明できない国債市場や格付け会社という不確実な存在にさらされている。こうしたリスクの中あっても、日本人は、限られた小さなパイの中の、限られた政策の中で、足し算と引き算に終始する矮小な思考から抜け出せない。経済のパイを広げるための産業創出や、イノベーションの惹起、科学技術の知能育成、教育制度の抜本的な変革といった、未来を切り拓く骨太で具体的な政策が出てこない。国家運営に携わる人たちが本気で自考しているとは思えない。
「国の未来を託せるまっとうな国会議員は、10人に1人くらいでしょうか?」。某党幹部に筆者はこう訊ねたことがある。すると、幹部は気色ばんで次のように答えた。「何を言ってるんですか。そんなにいるわけないでしょう」。国会議員とは、国民が依存する存在ではなく、我々国民がきちんと仕事をさせるよう促さなければならない存在だと捉えた方がいい。まっとうな国会議員は少数いるが、必要な政策がスムーズに実現しない仕組みにも問題がある。政官のみならず、日本経済を牽引するはずの大企業にも責任がある。大企業の内部留保の増加は思考停止の証左と言えないだろうか。これらが今の日本人のレベルである。我々のこの姿を謙虚に直視するところから始めなければならない。
4.「国家構想」と日本の創生
敗戦から80年。日本は本格的な国家構想を掲げた経験がない。未来への展望に不透明感が高まる今、国家構想を果敢に創るための自考を始める時機が来たのではなかろうか。国家構想とは、国家の理想的なあり方を長期的に見据え、変革や創生を進める理念や目標、政策の骨格である。現状の危機感と国づくりのモチベーションを国民と共有し、未来を展望できる国家構想を創ることができれば、活路が開けるのではないだろうか。そこで筆者は、独自の国家構想案について自考し、以下の5点を挙げてみた。いずれも即実践すべき政策だと考えている。
(1)教育制度の創生、(2) 産業創出、(3)日米同盟の再構築、(4)平和主義の徹底、(5)国際秩序の創生
(1)〔教育制度の創生〕戦後、日本人の学力の平均レベルを維持してきた教育制度は、明らかに子どもたちや現実社会の実状に追い付けなくなった。平均的な水準は比較的高いが、イノベーションが生まれにくく、抜きんでた才能が育ちにくい。先進国で異例の偏差値教育への傾倒は、比較主義や優劣という歪んだ概念を植え付ける副作用を生んだ。画一的で閉塞した教育制度の創り直しは、国の創り直しのベースになる。自主性、自律性、個性、多様性、創造性、共生、寛容性といったテーマがカギになろう。効果が形になるまで長期間を要するだけに、すぐ着手したい。例えば、教育制度の権限の多くを国から他都道府県に移譲する。質が高いフリースクールで過ごす時間を課程として積極的に義務教育に組み入れる。小学校から単位制を導入し、自主性や個性を伸ばす。いじめの遠因とも指摘される、固定したクラス制度を廃止する。多世代で多様な市民が互いを尊重し合い、地域と共に成長する「市民共育」のジャンルを創る。何よりも教員の質を高める。「子どもたちは本物の言葉に飢えている」。高校の元校長が筆者に語った、この一言がずっと胸に突き刺さっている。教員や我々大人の言葉が表面的で、薄っぺらいと指摘している。日本の現状を端的に表す言葉であろう。本質的な言葉を持ち、子どもや若者の可能性を最大限に引き出せる教員を輩出する仕組みが必要だと気付かされる。教員だけに委ねず、各分野の第一線の専門家がもっと教壇に立てる制度も求められよう。
(2)〔産業創出〕国会議員や官僚たちには、自分の足元にある小さな土俵だけで、限られた手元の材料だけで、足し引きする習性がある。土俵を広げたり、新たな土俵をゼロから創ったりする創造力が乏しい。アベノミクスについても、難易度が高い「成長戦略」を軽視し、「財政出動」と「金融緩和」に安易に依存し、失政に終わったという評価がエコノミストなどの間で広がる。衰退が進むこの期に及んでも、単なる減税やバラマキだけの議論に時間を費やすのは、創造力や実践力が乏しいと言わざるを得ない。そこで、産業創出である。かつて、自動車、洗濯機、テレビ、インターネットといった新しい製品やサービスをこの世に初めて生み出したように、新たな産業を創り出すことに国力を投入する。産業の新たなジャンルを創り、経済のパイを広げる。プレーヤーである企業が目を覚まして立ち上がり、それを政府が全面的に後押しする。この際、OECD加盟39カ国中、22位に低迷している「1人当たりGDP」を首位レベルに引き上げる目標を掲げるのもいい。産業創出による経済基盤の拡大は、行き詰った社会保障制度の立て直しにも直結する。また、必要な政策を迅速につくるために、政党の年功序列や党議拘束を原則、廃止するのはどうだろうか。
(3)〔日米同盟の再構築〕敗戦から80年。政治、経済の分野で、日本がアメリカから一定の“コントロール”を受けてきたことは紛れもない事実である。「日本が失った〇年」と例える際、筆者は「80年」を選ぶ。敗戦以降、アメリカが日本の自主性と自立性に干渉してきた80年をその根拠の一つと捉える。
アメリカと合理的な同盟関係を維持することは必要であろう。この際、日本が独立国家として自立することを前提とし、アメリカと対等の同盟関係に再構築することが避けて通れないと考える。いみじくも、トランプ政権は各国に防衛負担を求めている。日本としては、日米地位協定といった歪んだ“契約”を見直す必要もあろう。日本は基本的に自力だけで自国を防衛する体制を創る。そのために、アメリカ、中国などとの外交戦略も抜本的な変革が求められる。様々なハードルが待ち受けるが、与野党の一部の国会議員の中には、対等な日米同盟の再構築に確たる意志を持つ者もいる。
(4)〔平和主義の徹底〕ロシアのウクライナ侵攻や、イスラエルのガザ攻撃を止められない責任は、同じ地球市民として日本人にもある。戦争の痛みと虚しさを知る日本人には、全世界の平和を牽引する使命があるのではないだろうか。具体策として日本は、世界で類のない徹底した「永世中立国」を宣言し、そのアライアンスをアジア中心に広げる。この際、専守防衛を徹底するために、自力で国家を防衛する国に生まれ変わり、世界最高水準の防衛システムを構築する。日米同盟の再構築の一環として、在日米軍は段階的に撤収させる。そして、海外で大災害や大事故が起きた際、どこよりも速く現地に駆け付ける官民の「国際緊急救助隊」を格段に強化する。各国が攻撃をためらうような国民になるのである。また、広島に「世界平和大学」を創設する。この大学に世界中から、平和と戦争、共生や共存といった分野の研究者が参集し、平和を希求する学生が集う。そして、現下の戦争を直ちにやめさせ、戦争の芽を事前に摘み取るために、総力を挙げて強力なメッセージを発信し、強い行動を取り続ける。
(5)〔国際秩序の創生〕日本は「平和」「経済」を軸に、自由貿易と共生をテーマにした新たな国際秩序を構築する中核国として、その調和役・調整役を担う。トランプ政権によって、従来の国際秩序が崩れ始めた。臆することなく、多くの国々が参画できる新たな国際秩序を果敢に追求する。日本だけうまく立ち回れればいいという発想ではない。アメリカの孤立化を食い止めつつ、世界の共生や共存を念頭にした新たな国際秩序の創り直しを日本がリードする。こうした国家構想案の賛否を、ここで深く議論することが目的なのではない。国民や政府が国の創り直しに、早期かつ本気で着手する契機になればいいのである。
まとめ
「日本の再生」「日本の再興」というかけ声をよく耳にする。筆者はこの言葉に本気を感じない。「かつて元気だった時代を復活させたい」という懐古的な思考は、限界を伴う。過去に新しい解はない。現在に明確な解がないことも我々は感じ取っている。今、日本人に足りないのは、未来を創る視座であろう。国や社会の形を創り直すために、他者に依存せず、政府や国会議員にも依存せず、我々一人ひとりがそれぞれの持ち場で、未来に向けた自考を始めることが急務である。そろそろ目を覚ましたい。(了)(2025年7月)