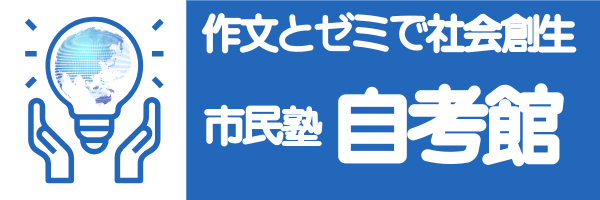甲子園で開催された今夏の高校野球は2年生の活躍が印象的でした。学年の壁を取り払って、下級生が上級生に遠慮せず、のびのびとプレーできる意識づくりに成功したチームが増えていると感じました。
日本社会にいま最も必要な組織づくり、チームづくりの示唆がありました。
決勝戦で闘った沖縄尚学と日大三高は、フラットな意識の浸透を象徴していたように思います。大会を主催した朝日新聞の記事からエピソードを抜粋して以下にまとめてみました。「2年生は9割ため口。(上下関係は)ほとんどないですよ」。後輩から「リツキ」と呼ばれる日大三高の本間律輝主将はこう言います。部員の多くは寮生活。差し入れのケーキがあれば、先に好きなものを選ぶのは1年生。自分の洗濯は自分でやり、掃除やグラウンド整備といった雑務は上級生ほど率先してやるんだそうです。三木有造監督は「後輩から『この先輩についていこう』と思われる先輩にならなきゃダメだよ」と言うそうです。
こうした日大三高の伝統は、小倉全由・前監督の時代から受け継がれているそうです。小倉さんが夜更けに洗濯場をのぞくと、下級生だけが洗濯をしていました。「二度とするな」と上級生を注意し、理不尽な慣習をなくしたそうです。この夏、準決勝で先発した2年生の根本智希投手は「これまで投げてくれている(3年生エース)近藤さんのために」と臨みました。ピンチで降板しましたが、近藤投手から「よく投げた。あとはまかせろ」と言われ、「3年生と1秒でも長く一緒に野球がしたい」と思ったそうです。2年生で4番の田中諒選手は先輩たちを愛称で呼びます。決勝は無安打に終わって涙し、先輩に支えられながら整列に加わりました。「自分のバットで(先輩を)勝たせてあげたかった」。
優勝した沖縄尚学は、末吉良丞投手と新垣有絃投手が2年生。選手たちは「自分たちの代から特に上下関係がなくなってきた」と口をそろえます。昨春、選手が日々感じたことを書く野球ノートで、「3年生がなるべく多くベンチに入れるように頑張りたい」と3年生が書きました。すると比嘉公也監督は選手全員を集め、諭したそうです。「学年で野球をしているわけじゃないよ」。下級生にも遠慮なくプレーしてほしいとの思いからでした。この言葉を胸に刻んだ今の3年生が、学年の壁を取り払ったといいます。
約10年前、経営破綻した航空会社スカイマークは、経営再建への取り組みの中で、従業員同士が、肩書ではなく、「さん付け」で呼び合うようにしました。スカイマークで働く知人から聞いたところ、「さん付け」で呼び合うことで、意識がフラットになり、部下であっても責任感が芽生え、仕事のモチベーションが職場で高まったのだそうです。「さん付け」運動だけの成果ではないでしょうが、スカイマークはその後、定時運航率で高い実績を続け、顧客満足度も上がりました。
日本人は、年齢や立場の上下などを踏まえて、遠慮したり、忖度したりすることを、〝美徳〟だととらえている人も多いと思います。外国から来た人から見れば、敬語、謙譲語などの使い方もややこしいでしょう。これも日本の文化です。目上の人を敬う文化はあっていいと思います。
しかし、年齢が上、学年が上、ポストが上というだけで、ふんぞり返って横柄な態度を取ったり、不合理な意思決定を押し付けたりするのは、組織の力を歪め、損うやり方として捉えられつつあるのではないでしょうか。日本人が直面している社会の衰退や閉塞感を打破するヒントを、甲子園の熱戦に見た気がします。(2025年8月)