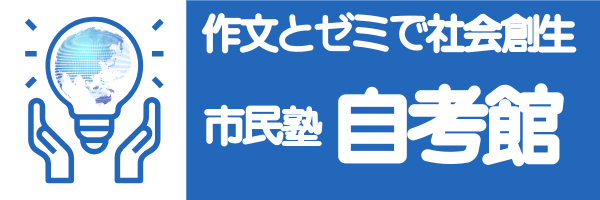痛みに耐えかねて、私の母は、病室を抜け出し、近くの踏切に向かいます。電車に飛び込もうと、覚束ない足取りでふらふらと踏切に向かいます。末期がんの母は、想像を絶する激痛に襲われていました。その激痛は、一縷の望みを母から奪おうとしていました。
「カーン、カーン、カーン」。踏切の音を、母はどんな気持ちで聞いたのでしょうか。電車がやってくる光景を、母は、どんな思いで見ていたのでしょうか。でも、母は、飛び込むのを思いとどまるのです。
油断したすきに病室を抜け出した母を、父はいつもの場所で見つけ、母をおんぶして、病室に戻ります。希望が次第に薄れていく闘病の日々。外出する体力を失った母は、今度は、部屋で鋭利なものを探し、それを手首に当てます。しかし、母が手首を切ることはありませんでした。
私が高校に入学した4月。病室から自宅に帰りたいと願った母は、やっと家に戻ることができました。その翌朝、母は、安心したように、ベッドの上で静かに息を引き取りました。1年半に及ぶ壮絶な闘病。私が志望校にたどり着き、姉も大学生になれたことを確かめるようにして、母は逝きました。
自ら命を絶つことを踏みとどまった母は、父にこう言ったそうです。「母親が自殺をしたら、子どもたちが可哀そうだから」。その強い思いを母は貫きました。その姿は、もう一つの言葉を私に投げかけてきます。「絶望の中にあっても、絶対にあきらめるんじゃないよ」。
これまで何があっても、私が自殺を選択することはありませんでした。これからもありません。激痛に耐え抜いた母の姿を思い浮かべると、自分で命を絶つことはできません。母の思いは、私の命を支える、いわばブレーキです。
新年を迎えた2025年1月。高校の同窓会で言葉を失いました。同期生のひとりが自殺したと知らされました。高校時代、彼は陸上部で活躍していたナイスガイ。しかし、妻子を残し、他界してしまいました。命を支えるブレーキは、その時、彼にはなかったのでしょう。
厚生労働省などによれば、2024年の1年間に自殺した人は2万268人に上りました。前年より減りましたが、高水準が続いています。一日あたり55.5人が自殺した計算になります。深刻なのは、小中高生の自殺が527人と過去最多になったことです。子どもが自殺する社会。若い世代の死因の上位は自殺です。日本の社会は、歪んでいるのだろうと、気付かされます。
2023年の自殺者の動機・原因について、全体で一番多かったのは「健康問題」。次いで「経済・生活問題」です。経済の衰退を背景に、日本人の貧しさの度合いは高まっていますから、自殺者が再び増加に転じることが懸念されます。
命を支えるブレーキをかける人の存在が必要です。命を支えるブレーキをかける仕組みを広げる施策が急務です。相談窓口などを紹介する目先の手立てだけでは、足りません。もっと希望が持てる社会に変えていかなければなりません。教育制度など社会システムの創り直しが不可欠でしょう。産業創出など本質的な経済政策を進めることも必要でしょう。日本社会のあり方が根源から問われています。(2025年1月)